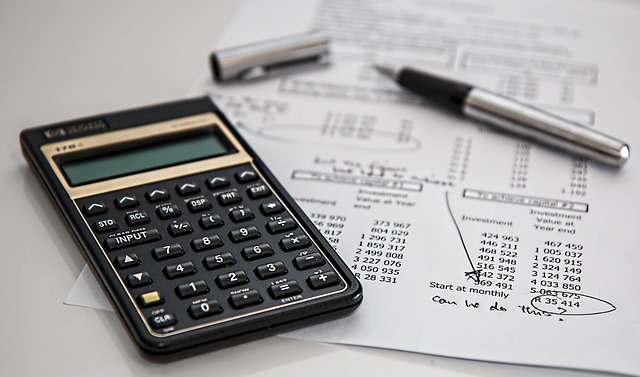
上場企業の経理はしんどい?激務?仕事内容や必要スキルを経験者が解説
- 上場企業の経理は仕事がきつい?
- 中小企業の経理とはどう違う?
- 上場企業の経理で働くメリットはどんなこと?
- 上場企業経理に転職成功するには?
上場企業の経理は、中小企業の経理とは仕事内容がかなり違います。
決算は年に4回ありますし、財務諸表の開示業務や会計士(監査法人)による監査への対応業務などもありますから、
はっきりいって仕事の難易度は高いと言えるでしょう。
しかし、上場企業経理として働くことには、
その困難さを超える達成感ややりがいがあるのも間違いありません。
会計についてのより深い知識を得ることができますし、
給料や福利厚生の面でも恵まれていると言えるでしょう。
この記事を通じて、上場企業の経理に興味はあるけれど不安を感じている方へ、私の経験をお話します。
この記事を書いた人
従業員が数千人規模の上場企業の経理部で働いています。
連結決算の情報をベースに公開資料の作成などの業務に従事しています。
上場企業経理で実際に働いていて感じることや、
求められる知識やスキルについて、実経験をもとにお話します。
kaikeijimusho-keikensha-ad↑
この記事の目次
日本の上場企業の占める位置

日本の上場企業の占める位置
日本の企業の数をご存知ですか?
中小企業庁によれば、中小企業の数は約421万社とされています。
上場企業は2023年11月のデータで、約3,900社です。
日本の企業の中で上場企業の割合は、約0.1%と非常に少ないです。
この限られた上場企業で経理を担当するには、知識だけでなく、タイミングも大切です。
私が最初に働いたのは上場を目指す企業で、上場企業の経理の要求を満たす仕事をしていました。
税効果会計や減損会計の知識が求められ、困難だったことを覚えています。
上場企業では経理以外の知識も大切
上場企業の経理では、経理財務以外の知識スキルも求められます。
具体的には、内部統制についての知識が重要ですね。
私はグループ子会社の経理も担当した経験がありますが、
上場企業の経理と比較すると難易度レベルにかなりの差があります(上場企業経理の方がきつい)
kaikeijimusho-keikensha-ad→
上場企業の経理における課題7つ

上場企業の経理における課題7つ
上場企業の経理の難しさを理解するためには、
↓以下の7つのポイントを知っておくと良いでしょう。
- 経理のスキルが高い人材の存在
- 管理会計と財務会計の深い理解
- 連結決算への深い知識
- 四半期ごとの決算実施
- 開示情報の手続き
- 監査への対応
- 高度な業務プロセス
1 .経理のスキルが高い人材の存在
上場企業の経理担当者は、日商簿記1級の知識が求められることが一般的です。
この資格が入社前から必要とは限らないものの、実務の中で必要性が増してきます。
非上場企業においても日商簿記1級レベルの取引は存在しますが、上場企業ではその比重が高まります。
多くの人が上場企業でのキャリアを希望する背景には、より専門的な知識を持つ人材と共に働ける魅力があります。
2. 管理会計と財務会計の深い理解
上場企業は、監査法人の審査を受け、投資家に対して業績データを公開する必要があります。
このため、財務会計と管理会計の知識が不可欠です。
- 財務会計:外部ステークホルダーに対する情報提供
- 管理会計:企業内での経営判断のための情報提供
財務会計の特徴
財務会計は、企業の外部ステークホルダーに対する報告を目的としています。
共通の会計基準に基づき作成されるため、異なる企業間の比較が可能です。
また、財務諸表は金融機関への提出時に正確である必要があり、間違いがあると信用問題につながる可能性があります。
管理会計の特徴
管理会計は、企業の経営計画の策定や経営の向上を目的としています。
経営陣はこれを基に意思決定を行います。
上場企業は、投資家に予算や業績を公表する必要があります。
企業公式サイトには、IR情報が公開されることが多いです。
そのため、管理会計の視点での業績分析や予算策定が求められます。
株主総会では、質問や指摘が多くなるため、十分な知識武装が必要です。
3. 連結決算への深い理解
多数の上場企業は子会社を保有しており、その場合、連結財務諸表の作成が求められます。
ただし、連結決算は単なる合算ではありません。
その主要な4つの要点を以下に示します。
- 内部取引の取り扱い
- 投資と資本の対応
- 未実現利益の考慮
- 会計表示の取り扱い
どの業界においても、上記の要点の理解が求められます。
連結決算の特性
連結決算は多くの作業を伴うため、専門家が分担して行うことが一般的です。
すべての作業を一人で把握することは難しいのですが、経理部門の管理者には全体像の理解が求められます。
連結決算に関する知識や経験は、
転職市場での評価が高いため、キャリアアップになります。
4. 四半期ごとの決算実施
上場している企業は、四半期ごとに決算を行う義務があります。
これは後ほど説明する通り、必要な情報を公開するためのものです。
非上場企業は、通常、年1回の決算で税額を確定します。
一見、4倍の作業と思われるかもしれませんが、それほど複雑ではありません。
決算時には、エラーや不整合がないように情報を整理する必要があります。
ただ、年度末を除き、影響の少ないミスは調整期間中に訂正することが多いです。
エラーの重要性について
エラーを容認するものではありませんが、年次決算での正確な情報開示が最終的な目的です。
そのため、些細なエラーは大目に見られることもあります。
さらに、税金の計算には簡略化された方法も存在します。
具体的には、課税前の収益に特定の税率を適用して計算できます。
四半期ごとの決算は、作業の効率化にもつながります。
3か月ごとに繰り返すことで作業スキルが向上し、時間の短縮を期待できます。
5. 決算開示の手続き
決算書をまとめた後、公開する資料を整理します。
開示資料の種類には違いがありますが、主要なものは以下の5つです。
- 決算短信
- 四半期報告書
- 有価証券報告書
- コーポレートガバナンス報告書
- 内部統制報告書
「四半期決算」では、決算短信、四半期報告書、
内部統制報告書を決算日の翌日から45日以内に公表します。
「年次決算」においては、決算短信は45日以内、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書、内部統制報告書は3か月以内に公開されます。
有価証券報告書のボリューム
多くの企業で有価証券報告書は100ページ以上のボリュームを持ちます。
作成は難しいものの、それと同じくらい確認作業も大変です。
非上場企業にはこの資料の作成義務がなく、ほとんどの企業では取り組んでいません。
年次決算では、多くの資料を整理する作業が増えるため、労力が必要です。
しかし、この経験は専門的なスキルを身につけることができるため、達成感もあります。
6. 監査への対応
公開する資料には監査法人の認可が必要です。
以下の手順で進められます。
- 連結決算書の作成
- 開示資料の整備
- 監査法人の確認
- 投資家への公開
公表前に、監査法人から資料の確認を受け、詳細な質問を受けることもあります。
子会社の会計処理も監査の対象
子会社の会計も正確性が求められるため、
決算を迎えるにあたり、子会社の指導も欠かせません。
監査法人からの認可取得は難しいものの、
監査のすべてのステップを理解している担当者は珍しく、
転職時にも高く評価されるポイントとなります。
7. 高度な業務プロセス
上場企業では、結果だけでなく、業務のプロセスも評価される要素となります。
多くの場合、業務手順書を作成し、
正確な作業が実施されているかを確認することが求められます。
「こんなに詳しく確認する必要あるの?」と疑問に思うかもしれませんが、
手順書と実際の作業が一致していない場合、それは問題とされます。
一度のミスだけで「不適切な決算書」とはなりませんが、
繰り返しミスが発生すると監査法人からの厳しい指摘を受けることとなります。
「そこまで厳密に行う必要があるか?」と思うかもしれません。
エラーや不正を避けるため、
上場企業においてはこういったミスのチェックは非常に厳格に行う必要があります。
kaikeijimusho-keikensha-ad→
上場企業経理で働くことの魅力5選

上場企業における経理の魅力5選
上場企業における経理のポジションには5つの大きな利点が存在します。
「上場企業での仕事は多岐にわたり大変だ」と思うかもしれませんが、上場企業での経験は非常に価値があるのです。
それを活用すれば、キャリアアップの手助けとなります。
また、上場企業の多くは福利厚生が手厚く、そういった点も魅力的です。
私自身、東証一部の企業に所属しているので、そこで感じた上場企業の利点を5つお伝えします。
- 充実した福利厚生
- 社会的信用度の高さ
- 専門的知識の習得
- 会社の業績の透明性
- 持株会の存在
1. 充実した福利厚生
上場企業は、スタートアップとは異なり、経営基盤が安定しています。
その結果、収益を株主だけでなく、社員にも還元することが多いです。
社員への還元を通じて、働く意欲を高め、更なる業績の向上を目指します。
以下は福利厚生の一部です。
- グループ割引
- 旅行会社提携特典
- カフェテリア利用
- 長期休暇の提供
- 共済の存在
- 退職金制度
福利厚生は企業ごとに異なり、良い人材を確保してモチベーションを維持するための独自の制度も実施されています。
その中には社員同士の交流を促すものもあり、給与だけでは得られない喜びがあると感じます。
2. 社会的信用が高い
上場企業に勤めると、その社会的な信用度を感じる瞬間があります。
たとえば、ローンを組む際、以下の3点が評価されます。
- 年収
- 勤務先の企業名
- 勤務年数
金融機関は「返済能力があり、安定した企業に所属しているか?」を重視します。
業績が公開されている
上場企業では、業績データが公開されています。
そのため、企業の評価が明確です。
有名な企業や急成長している企業では、
信用度が高まり、ローンの金利も低くなることが期待できます。
3. 専門知識が身につく
前述した通り、上場企業での経理業務には、連結財務諸表の知識が求められます。
特定のスキルが必要とされるので、関与する人数も限られています。
2023年3月末時点での上場企業の数は約4,000社です。
そのうち経理業務に携わる人数を一社あたり平均3人程度とすると、約12,000人となります。
これは、日本の労働人口の約0.0002%であり、その専門性の高さがわかります。
4. 会社の業績が透明
上場企業は、四半期ごとに決算情報を公開します。
一方、非上場企業の情報は官報に掲載されるものの、詳細性に欠ける場合があります。
上場企業では、監査法人による確認済みの正確なデータが提供されるので、その真実性に自信を持つことができます。
5. 持株会の存在
上場している会社には、自らの株を取得する社員持株制度が存在します。
社員持株制度として、毎月の給料から特定の金額を引き落とし、会社の株式を取得することが認められています。
また、取得した金額の5%〜10%が奨励金として追加されることがあります。
たとえば、10,000円分の株式を取得し、奨励金が10%の場合、11,000円分の株式を取得することになります。
この1,000円は会社が負担します。
複利の恩恵は考えにくいですが、10%の奨励は魅力的です。
多数の会社で、5%〜10%の奨励が設けられているのは一般的です。
kaikeijimusho-keikensha-ad→
上場企業の経理部門への3つの就職・転職方法

上場企業の経理部門への3つの就職方法
上場企業の経理部門に魅力を感じることができましたか?
ここで、上場企業で経理業務に携わる3つの方法をお伝えします。
- 転職を考える
- 新卒採用を目指す
- 知り合いの推薦を受ける
①転職を考える
もっとも一般的な方法は、転職を通じて上場企業の経理部門で勤務することです。
転職を検討する際は、以下の2つが考えられます。
- 転職サイトを利用する
- 転職エージェント経由で応募する
募集している会社の背景を考慮すると、
人材の補充が必要であることが伺えます。
主な理由として以下の4点が挙げられます。
- 職員の退職
- 職員の産休・育休等の一時的な人手不足
- 業務の拡大
- 次世代のリーダーの育成
多くの場合、職員の退職が主な理由です。
経理は安定した職種ですが、人間関係の問題で退職することもあります。
上場企業の経理部門の責任者は個性的な方が多く、相性によっては難しい環境になることもあります。
他の理由は基本的に肯定的なものです。
そのため、あなたに合った環境が見つかる可能性は高いです。
2. 新卒採用を目指す
もしあなたが学生であれば、新卒として採用されて経理部門に配属される方法もあります。
新卒の場合、希望する部署を伝えることができますが、最終的には会社の判断に委ねられます。
また、経理部門は安定しており、大企業であっても頻繁に人員の追加は行われません。
簿記の資格を持ち、連結決算に関する知識があれば、希望する部署に配属される可能性が高まります。
3. 知り合いの推薦を受ける(コネ入社)
3つの方法の中でもっとも確率は低いですが、人脈を活かして経理部門を目指す方法です。
若い時期は難しいですが、40代になると、人脈で上場企業の経理部門の責任者を紹介してもらうえるケースもあります。
また、監査法人や税理士からの紹介も考えられます。
紹介を受けるためには、上場企業の会計経験があると好まれます。
しかし、これまでの経験と知識を評価してもらうことで、
未経験でも上場企業での勤務の機会は十分に考えられます。
上場企業の経理部門での未経験者の役割
たとえば、上場子会社の経理部門で親会社へのデータ提供を担当している者は、そのデータがどんな目的で利用されるかを把握しているケースがあります。
このような人は、親会社の業務内容を迅速につかむことが可能です。
親会社に所属していると、子会社で生じる具体的な課題や状況を完全に理解するのは難しいです。
そのため、子会社の経理部門での勤務経験は、親会社での業務遂行にも有利に作用することがあります。
kaikeijimusho-keikensha-ad→
上場企業の実際の求人で求められる仕事内容
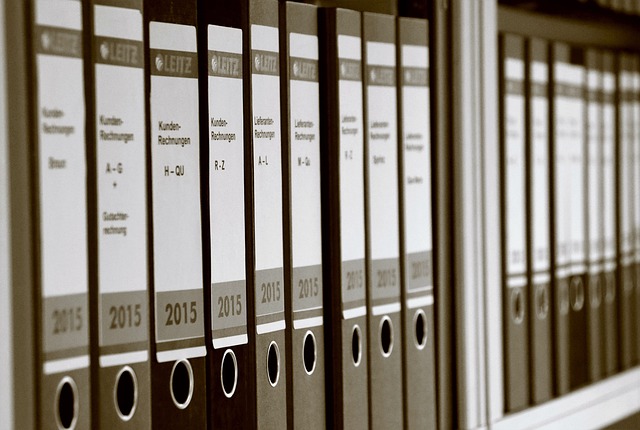
上場企業の3つの募集内容
上場企業での実際の求人はどんなものでしょうか?
上場企業が経理のスタッフを募集する際の3つの内容をピックアップしました。
これらのポイントを詳しく、どのようなタスクがあるかを説明します。
上場企業の募集内容①
- 決算タスク(月次決算、四半期決算、年次決算)
- 日常のタスク(仕訳、経費の精算、資金の管理、負債管理、資産管理業務)
- 公開タスク(決算短信、四半期報告書、有価証券報告書の作成等)
この職務内容は直接的で、上場企業の一般的なタスクをリストアップしています。
関連する子会社は少なく、メインの担当者としての役割が期待されます。
大きなプロジェクトに関与する場合、
監査対応や子会社への指導などが含まれることが多いです。
上場企業の募集内容②
- 連結決算業務、財務レポートの作成
- 有価証券報告、IR関連資料の作成
- 監査法人や他の関係者との対応
- 連結子会社や関連会社への経理指導や改善提案
- 財務戦略の立案や推進(プロジェクト運営など)
- 一般的な経理・財務管理業務
このタスクリストは①のものよりも詳細で、
監査対応や子会社の経理指導などが追加されています。
上場企業の募集内容③
- 個別およびグループの決算
- 会計と内部監査の対応
- 開示情報の提供(会社法・証券取引法)
- 税務タスク(グループ課税、税務調査対応等)
- 管理会計(部門別のコスト計算や月次決算等)
- 新たな投資やM&Aに関連する会計や税務対応
- 新しい会計基準や経理関連のシステム導入のプロジェクト対応
仕事内容についてのまとめ
3つのタスクを詳しく解説しました。
求人内容を確認すると、どんな仕事が待っているのかが想像できます。
これらのタスクに挑戦してみたいと思いませんか?新しいタスクは最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れると充実感を感じることができます。
kaikeijimusho-keikensha-ad→
経験からの上場企業の経理についての考察

経験からの上場企業の経理についての考察
私が経験した上場企業の経理に関して、
親会社と子会社の両面からの見解をお伝えします。
子会社の経理
子会社の経理に関する業務は、
財務諸表の作成に関する要件は親会社と変わらない印象でした。
四半期決算も親会社と同じ頻度で行われます。
キャッシュフローに関しては、必要な変動をすべて通知することが必要です。
この項目に関しては、特定の変動が求められることを認識しました。
親会社との主な違いは、開示関連業務に関する知識が、子会社側ではほとんど要求されない点です。
親会社の経理
親会社での経理について、子会社の経理知識で基本的に十分であるとの印象を受けました。
しかし、子会社では稀な取引、たとえば有価証券の取得や不動産の管理などがあり、それらの取引を理解することが求められます。
開示に関する情報提供は、子会社と大差なく、特別な追加知識は不要でした。
ただ、連結決算を行う際には、独自の知識が求められることもありました。
子会社と親会社の経理の対比
私の経験から、子会社と親会社の経理の知識に大きな差異は見られませんでした。
報告内容もほぼ同じですが、主な違いは連結決算に関する知識や、開示に関する知識の求められることです。
とくに、開示に関する知識は親会社での経験がないと習得が難しいです。
kaikeijimusho-keikensha-ad→
まとめ

「上場企業の経理の難易度」の総括
上場企業の経理の特徴について詳しく触れたので、こちらで要点をまとめます。
上場企業での経理業務の難しさは、高度な会計技術と連結決算の専門性にあります。
ただ、この難しさこそが仕事の醍醐味でもあります。
上場企業の魅力は、福利厚生の充実と公的な信頼性にあります。
福利厚生は、給料だけでは得られない満足感につながります。
上場企業の経理のポストを目指す場合、転職は1つの方法です。
経験がなくても、会計や税務の高度な知識があれば、採用のチャンスはあります。
連結決算を含む経理業務には、税務、会計、連結の3つの知識が求められます。
私自身、連結業務未経験から上場企業に転職し、現在は連結決算を担当しています。
また、監査法人とも連携しています。
経理のキャリアをスタートしたころは、現在のポジションにいることを想像もしていませんでした。
それだけに、今は驚きと喜びでいっぱいです。
上場企業の経理に関心がある方は、ぜひ挑戦してみてください。
kaikeijimusho-keikensha-ad↓